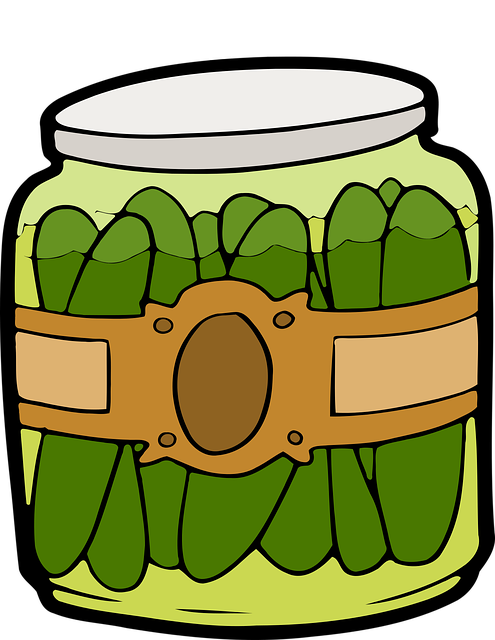こんにちは。monakaです。
なんとなく発酵食品は良いらしいと聞いたことがあるでしょうか?
発酵食品はすごいです。なぜなら、 <微生物の力をまるぱくり> できるから。
どういうことなのか、発酵食品にはどんなものがあるのか、豆知識をたくさんご紹介しますね。
発酵食品とは?
発酵食品とは、微生物の働きによって食品の成分が分解・変化し、うま味や香り、栄養価が高まった食べ物のことです。
納豆や味噌、ヨーグルトのように、日本や世界各国で古くから親しまれてきました。
食品+微生物→→→発酵食品(おいしい)
微生物は自分たちが生きるために食品に住み着きます。そして食べます。微生物によって、食品は分解されます。
その変化の結果、私たちが口にして「おいしい」と感じるものが発酵食品、「食べられない」と感じるものは腐敗と呼ばれます。
腐敗との違い
発酵と腐敗は、どちらも微生物が食品の成分を分解する現象ですが、その結果が大きく異なります。
発酵は、乳酸菌や酵母など有益な微生物が働き、香りや味、保存性を向上させます。
一方、腐敗は有害な微生物が繁殖し、悪臭や変色、有毒物質を発生させます。
つまり、発酵は人間にとってプラスの変化、腐敗はマイナスの変化と考えると分かりやすいでしょう。
面白いことに、発酵と腐敗の境界は人間の嗜好や文化によっても左右されます。
例えば、納豆やブルーチーズは日本や欧米では発酵食品として親しまれますが、他の地域では「腐っている」と感じられることもあります。
日本人でも、納豆が嫌いという人は一定数います。関西ではあまり好まれないようですね。
発酵食品のメリット
発酵食品には、健康や美容、食生活にうれしい効果がたくさんあります。
まず、発酵によって食品は、体内で吸収されやすくなります。
⇒発酵食品は微生物によって分解されているので、食べた後の消化吸収がしやすい!
例えば、発酵大豆の納豆や味噌は、たんぱく質が分解されてアミノ酸になり、消化がスムーズです。
また、乳酸菌やビフィズス菌などの善玉菌が腸内環境を整え、便通改善や免疫力アップに役立つとされています。
⇒発酵食品内の微生物そのものも、腸活を支えてくれる!お通じ改善&風邪をひきにくく!
さらに、発酵過程で生まれる独特の香りやうま味成分が、料理全体の風味を引き立てます。
微生物は生きるために分解(発酵)という名の食事をするのですが、この時に副産物として嬉しい成分が作られたりするわけです。
ビタミンとかアルコールとかアミノ酸などなど。納豆の血液さらさら成分も、栄養たっぷりの甘酒も、旨味満点のかつお節も全部微生物たちのおかげです。
⇒発酵食品には微生物が作り出した栄養や、旨み成分がたっぷり!
加えて、発酵食品は保存性が高く、長持ちします。冷蔵技術のなかった時代から食材を長く安全に保つ知恵として重宝されてきました。
それは、微生物が食べ物を分解するときに「酸」や「アルコール」を作るからです。
酸やアルコールが、他の菌(食べ物を腐らせるような悪い菌)が増えることを抑えます。なので、発酵食品は長持ちするのです。
⇒発酵食品は保存性が高い!
発酵食品を毎日の食生活に自然に取り入れて、おいしく健康な日々を過ごしましょう。
発酵の種類
発酵は、使われる微生物や生成される成分によって大きく3つに分類されます。
1つ目は「乳酸発酵」。
乳酸菌が糖を分解して乳酸を生成し、酸味と保存性を高めます。ヨーグルトやキムチ、漬物などが代表例です。
2つ目は「アルコール発酵」。
酵母が糖をアルコールと二酸化炭素に変えるもので、日本酒やビール、ワイン、パンづくりにも利用されます。
3つ目は「酢酸発酵」。
酢酸菌がアルコールを酢酸に変え、爽やかな酸味を生み出します。お酢やコンブチャがこれに当たります。
ほかにも、納豆菌や麹菌などが関わる発酵もあり、食品によって複数の発酵が組み合わさることもあります。
全部知ってる?発酵食品一覧
発酵食品と聞くと、思い浮かぶものはなんでしょうか?ヨーグルト?納豆?味噌?
私たちが毎日のように使っている調味料やお菓子、飲み物にはたくさんの発酵の力が隠れています。
ジャンル別に代表的な発酵食品を一覧でご紹介します。
知っているものから意外な食品まで、あなたの発酵食品のイメージがきっと変わりますよ。
調味料編
発酵の魅力を最も身近に感じられるのが調味料です。
・味噌
味噌は大豆を麹菌で発酵させた、日本の伝統的な発酵食品。たんぱく質が分解されてうま味成分であるアミノ酸が豊富になります。
・醤油
醤油も味噌と同じく大豆と小麦を麹菌で発酵させ、香り高い風味を生み出します。
・酢
お酢はアルコールを酢酸発酵させて作られ、料理に爽やかな酸味を加えるだけでなく、防腐効果もあります。
・みりん
みりんも発酵食品です。もち米と米麹を発酵させて作られた甘みと香りが特徴。
さらに、魚介を発酵させたナンプラーやしょっつるなどの魚醤は、アジア各地の料理に欠かせません。
これらの調味料は、単なる味付けだけでなく、栄養や保存性、料理の深みを支える存在です。
普段何気なく使っている調味料が、実は何百年も受け継がれてきた発酵の知恵だと知ると、味わい方も少し変わってくるでしょう。
乳製品編
・ヨーグルト
乳製品の発酵食品といえば、やはりヨーグルトが代表的です。乳酸菌が乳糖を分解し、酸味ととろみを生み出します。乳酸発酵によって腸内環境を整える効果も期待できます。
・チーズ
チーズも牛乳や羊乳などを発酵・熟成させて作られ、種類によって味や香りが大きく異なります。熟成の度合いやカビの種類によって、まろやかなものからブルーチーズのように個性的なものまで楽しめます。
・バター
バターは本来発酵食品ではありませんが、「発酵バター」は乳酸菌を加えて発酵させたもので、コクと香りが豊かです。
さらに、ヨーグルトに似た「ケフィア」や、酸味が特徴の「サワークリーム」も発酵乳製品の仲間。これらはデザートやパン、料理に幅広く活用できます。
野菜編
・ぬか漬け
ぬか漬けは、米ぬかに塩・水・昆布・唐辛子などを混ぜて作る「ぬか床」に野菜を漬け込み、乳酸菌や酵母などの微生物が野菜の糖分を分解して発酵させます。ビタミンB群が豊富です。
・キムチ
キムチは、白菜や大根などの野菜を塩漬けにして水分を抜き、唐辛子やニンニク、生姜、魚介の塩辛などを混ぜて漬け込みます。野菜や調味料に含まれる糖分を乳酸菌が分解し、発酵が進みます。
・ザワークラウト
ヨーロッパでは、キャベツを乳酸発酵させた「ザワークラウト」が人気で、ソーセージや肉料理の付け合わせとして定番です。
・すんき漬け
すんき漬けは、長野県木曽地方の伝統的な漬物です。塩を一切使わない乳酸発酵が特徴です。
赤かぶ菜(赤カブの葉)を蒸してから、前の年に作ったすんきを「種すんき」として加え、暖かい場所で発酵させます。
この「種すんき」に含まれる乳酸菌が野菜の糖分を分解し、自然な酸味とうま味を生み出します。
・野沢菜漬け
野沢菜漬けは、長野県野沢温泉村発祥とされる漬物で、冬の保存食として古くから親しまれています。
収穫した野沢菜を塩漬けにし、時間をかけて乳酸菌による乳酸発酵を行うことで、独特の酸味とうま味が生まれます。
このように、地域ごとに独自の発酵野菜文化があります。
発酵によって食物繊維やビタミンCが壊れにくくなり、保存期間も延びるため、冬の保存食として重宝されてきました。
発酵野菜はサラダ感覚で食べられるものも多く、現代の食卓でもご飯のお供として、手軽に取り入れられます。
穀物・豆類編
穀物や豆類も、発酵によって全く新しい味や食感に生まれ変わります。
日本を代表するのは「納豆」。納豆菌が大豆を発酵させ、特有の粘りと香り、そしてナットウキナーゼなどの健康成分を生み出します。
インドネシアの「テンペ」も大豆を発酵させた食品で、クセが少なく肉のような食感からベジタリアン料理にも重宝されています。
甘酒は米や米麹を発酵させた飲み物で、アルコールを含まないタイプは「飲む点滴」とも呼ばれ、消化吸収の良いブドウ糖やアミノ酸を含みます。
パンやクラッカーの生地も発酵を利用しています。小麦粉を酵母で発酵させることでふっくらとした食感と香りが生まれます。
豆味噌や赤味噌なども大豆発酵食品の仲間で、地域ごとの味の違いが楽しめますよ。
魚介類編
魚介類の発酵食品は、保存の知恵と独特の風味が光ります。
日本では、魚を麹や塩で発酵させた「塩辛」や「魚醤(しょっつる、いしる)」が有名です。
東南アジアでは「ナンプラー」や「ヌクマム」が料理のうま味の源として広く使われています。
また、鰹を発酵・乾燥・燻製させた「かつお節」は、世界的にも珍しい硬さと香りを誇り、日本のだし文化を支えています。
滋賀県の郷土食「鮒寿司」は、塩漬けしたフナとご飯を乳酸発酵させた伝統食品で、チーズのような香りと酸味が特徴です。
韓国の「アミの塩辛」や北欧の「シュールストレミング(発酵ニシン)」のように、香りの強さから好き嫌いが分かれるものも多いですが、それぞれの地域で長く愛されてきた味わいです。
魚介発酵食品は料理に深いコクを与え、少量でも満足感を高めます。
飲み物編
発酵食品は、私たちの喉を潤す飲み物にもたくさん隠れています。
日本酒やビール、ワインは有名ですが、発酵飲料の世界はもっと広いです。
近年人気の「コンブチャ」は紅茶や緑茶を酢酸菌と酵母で発酵させたもので、甘酸っぱく爽やかな味わいと健康効果で注目されています。
韓国では「マッコリ」、中東や中央アジアでは「クムス(馬乳酒)」など、地域ごとに個性豊かな発酵飲料があります。
コーヒー豆やカカオ豆も収穫後に発酵工程を経て風味を引き出しています。実はコーヒーやココアも発酵の恩恵を受けている飲み物なんです。
甘酒や乳酸菌飲料のようにアルコールを含まない発酵飲料もあり、子どもから大人まで楽しめます。
お菓子・スイーツ編
「お菓子に発酵食品?」と思うかもしれませんが、意外と多くのスイーツが発酵の力を借りています。
例えば、パンケーキやドーナツなどはイースト発酵や天然酵母によってふんわり仕上がります。
洋菓子に欠かせない「発酵バター」は乳酸菌発酵による豊かな香りが特徴で、クロワッサンやフィナンシェなどの風味を格段に引き上げます。
和菓子の餡も、小豆を煮た後に発酵させて熟成風味を出す製法が使われることがあります。
チョコレートも発酵食品の一種です。チョコレートの原料であるカカオ豆は発酵を経て香り成分が生まれるのです。
お菓子やスイーツは甘さが主役ですが、その奥にある深い香りやコクは、発酵の力によるものが少なくありません。
意外な発酵食品ベスト5
「これ、発酵食品だったの!?」と思わず驚く食品は意外と多いものです。
ここでは、日常的に口にしているのに発酵のイメージが薄い食べ物や、珍しい発酵過程を経る食品をランキング形式でご紹介します。
話のネタにしてください。
第5位:コーヒー
コーヒー豆は、コーヒーの木になる赤い実(コーヒーチェリー)の中にある種子です。収穫後、この果肉を取り除く際に発酵が行われます。
発酵方法は主に3つ。
1. ウォッシュド(湿式発酵)
果肉を除いた後、豆の周りに残る粘液質(ミューシレージ)を水槽の中で乳酸菌や酵母などの微生物によって発酵させ、分解します。
2. ナチュラル(乾式発酵)
果肉をつけたまま天日で乾燥させる間に、果実内で自然発酵が進みます。
3. ハニープロセス
果肉は除去するが粘液質は残し、乾燥させながら発酵させる中間的な方法。
これらの工程がコーヒーの香りやコクを引き出し、味わいの個性を決めます。
第4位:チョコレート
カカオ豆は収穫後、バナナの葉や木箱に入れ、自然に存在する酵母や乳酸菌、酢酸菌で発酵させます(約2〜7日)。
発酵後に天日干しや乾燥機で水分を抜き、その後焙煎することで本格的なチョコレートの香りが完成します。
カカオ豆の発酵はチョコレートの味・香り・質感を決定づける不可欠な工程です。
発酵の方法や時間が違えば、同じ品種でもまったく違う風味のチョコレートになります。
第3位:かつお節
カツオを煮て乾燥させた後、カビ付けと発酵を繰り返して作られる、世界でも珍しい発酵食品。
カツオ節カビ(アスペルギルス属)は鰹の表面のたんぱく質や脂肪を分解し、旨味成分(アミノ酸)や香りを生み出します。
また、カビが水分を吸って乾燥を助け、保存性も高めます。
かつお節は、燻製×乾燥×発酵の3つの工程を組み合わせて作られます。
日本の発酵技術の集大成ともいえる存在です。
硬さ・香り・旨味のすべてが凝縮され、日本のだし文化を支えています。
第2位:紅茶
ここでいう「発酵」は乳酸菌や酵母による微生物発酵ではなく、茶葉中の酵素による酸化反応を指します。
紅茶は茶葉を完全発酵させることで、渋みがまろやかになり、独特の香りが生まれます。緑茶との違いは、この発酵工程の有無にあります。
紅茶の場合、「発酵」という言葉は伝統的に使われていますが、実際には微生物ではなく酵素による酸化反応がメインです。
それでも、風味作りという意味では発酵食品と同じ“変化”です。
第1位:パン
「パンって発酵食品だったの!?」と思う人も多いはず。
ドライイーストでパンを作ったことがありますが、たしかに「一次発酵」「二次発酵」という単語があった気がします。
でも、筆者は発酵食品とは認識していませんでした。
酵母菌が糖をアルコールと二酸化炭素に変え、生地をふっくら膨らませます。アルコール は 焼成中に揮発し、風味の一部を形成します。
焼き上がった香りや柔らかさは、酵母による発酵のおかげです。
まとめ|毎日の食生活に発酵食品を取り入れよう
発酵食品は、味や香りを豊かにするだけでなく、栄養価や保存性を高め、腸内環境の改善や免疫力アップなど健康面でもさまざまなメリットがあります。
日本や世界には、納豆や味噌、ヨーグルトといった定番の発酵食品から、コーヒーやチョコレートのような意外なものまで幅広く存在します。
日常の食卓に少しずつ取り入れるだけでも、料理の味わいが増し、健康習慣にもつながります。
まずは調味料や飲み物、乳製品など身近な発酵食品から試してみると、手軽に発酵の魅力を楽しめます。
毎日の食生活に発酵食品を取り入れて、体も心も満たされる食体験を始めましょう。